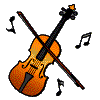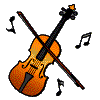今回のコンサートのプログラムの出発点は、フランス現代の作曲家、それもまだ8年前
の1986年に亡くなったばかりのデュリュフレでした。今、世界で静かなブームとなってい
るグレゴリオ聖歌の旋法とリズムを、近代的な響きに結び合わせた作風を持ち、今日演奏
される「グレゴリオ聖歌の主題による四つのモテット」もグレゴリオ聖歌をテーマとして
作曲されています。同じデュカスの門下生の中に、6歳年下のメシアンがいるというのも
興味深いことの一つです。
デュリュフレから時代を遡り、第1次世界大戦後活躍したフランス6人組の中でも、大
作を残しているオネゲル、近代フランス音楽において重要な位置を占めるラヴェル、さら
にその基礎を築いたサン・サーンス、ロマン派後期のグノーと今回はフランスの合唱曲を
プログラムの前半におくことになりました。
オネゲルはスイス人を両親としてフランスで生まれ、パリとチューリッヒで音楽を学び
ました。本日、歌いますのは「クリスマス・カンタータ」の後半の部分で、ラテン語、フ
ランス語、ドイツ語の入り交じったスケールの大きな作品で、「きよしこの夜」などのク
リスマス・キャロルや中世のグレゴリオ聖歌など、耳に親しいメロディーが織り込まれて
います。
ラヴェルといえば「ボレロ」があまりにも有名ですが、合唱曲にもラヴェルらしい色彩
感あふれる作品が残されています。「三つのシャンソン」の詩はラヴェル自身が書いたも
ので、アイロニーあふれるものになっています。
サン・サーンスもまた「動物の謝肉祭」の“白鳥”で知られた作曲家ですが、作品68と
呼ばれるこの二つの合唱曲は、ア・カペラ(無伴奏)のロマンティックな美しい小品で、
敬愛するグノーに捧げられたものといわれています。
グノーの「バビロン河のほとりで」は、イタリア語で歌われる厚みのある響きがとても
魅力的な曲です。「バビロン河のほとりで」といえば、パレストリーナの名曲があります
が、それとは少し視点を変えたところで作曲されています。グノーは、若い頃にローマに
留学し、パレストリーナなどの教会合唱曲の研究をしていたということです。
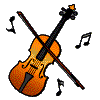
後半のステージは、日本の現代作曲家の二つの作品をとりあげます。
まず最初の「春の予感」は、昨年に続き木下牧子氏の作品で、四季の色合いが器楽曲的
に描き分けられた八つの曲が、自然の姿を浮かび上がらせていきます。アルベルネでは、
これまでにも何度か取り上げてきた作曲家ですが、初めてのア・カペラで、新たな一面に
触れることができました。
最後のステージは、アルベルネが初めて演奏する作曲家・吉岡弘行氏の「風の詩集」で
す。古典に忠実な音楽作りの中に、若々しい感性のあふれる爽やかな組曲で、
第1曲「風の言葉」 :リズミックで溌刺とした曲。しなやかに風は吹きぬける。
第2曲「風の子守うた」 :ハバネラのリズムに乗ったアンニュイな曲。平易な詩の
中にも子供への愛情が満ちてくる。
第3曲「風のオーケストラ」:ヴァイオリンやトランペット、フルートが風に乗せて
ワルツを奏で、いつしかオーケストラになっていく。
第4曲「風のまち」 :バラード風の終曲。力強く、またノスタルジックに歌わ
れる。 (楽譜のまえがきよりの抜粋)
と続きます。1992年に初演された新しい作品で、今回が出版による改訂新版の初演にあた
ります。
(濱田和昭)
 ☆プロフィールへ☆
☆プロフィールへ☆