鳥について 安水 稔和
わたしがまだ若い頃、25・6歳の頃、鳥のことばかり書いた時期があった。
原稿用紙を広げてまず鳥と書いた。鳥と書くと不思議に言葉の扉が開いた。次々と鳥が現
われた。飛ぶ鳥。いつまでも飛び続ける鳥。落ちる鳥。歩く鳥。走る鳥。いつまでたって
も飛べない鳥。坐りこんだ鳥。動かない鳥。羽根のない鳥。泥だらけの鳥。投げこまれた
礫。さまざまの鳥たちが日常の世界を駆け抜け、非日常の世界へ飛び立った。
鳥は鳥であって、わたしであって、あなたであって、わたしたちであった。鳥は言葉で
あり、声であり、歌であった。そんな鳥たちを集めて詩集を作った。詩集の題を『鳥』と
した。詩集に閉じこめたはずの鳥たちは、その後も、事あるごとに現われた。
さまざまの姿態で、今も。
あの鳥影に言の葉を引き結べば
日影揺れる戸口に
なつかしい人が立つという
わずかに血のにおう
あなたの眉のあたりをまた
鳥の影が過ぎる (「春は鳥占」終連)
このたびの合唱組曲「鳥について」の詩はいずれも1956年から7年にかけて書いたもの
である。「鳥よ」3篇と「飛ぶ意志」は詩集『鳥』(1958年刊)から、第4曲「歌」は詩
集『愛について』(1956年刊)から池辺晋一郎さんが選び取られた。半世紀近く前に飛び
立ったわたしの言葉たちが、池辺さんによって新しい翼を与えられ、池田明良さんとアル
ベルネ・ユーゲント・コールの皆さんによってあらためて飛び立つことになった。
こんな嬉しいことはない。
鳥になれ
鳥よ。 (「鳥よ」結び)
◇ ◇ ◇ ◇
安水稔和氏のプロフィール
神戸市生まれ、神戸大学文学部卒業、神戸在住。
詩集「愛について」「鳥」「記憶めくり」(地球賞)「秋山抄」(丸山豊記念現代詩賞)
「いきているということ」(土井晩翆賞)など17冊。昨99年「安水稔和全詩集」(沖積
舎)が刊行された。他に評論集12冊やラジオドラマ「旅に病んで」(芸術祭優秀賞)、
合唱組曲「京都」(芸術祭奨励賞)など放送作品、舞台作品も多い、詩誌「火曜日」発
行人、詩誌「歴程」同人。
神戸松陰女子学院大学助教授。日本現代詩人会会員。兵庫県現代詩協会会長。日本著作
権協会会員。

「鳥について」について 池辺 晋一郎
合唱の作曲は、詩がなければ始まらない。いや、しょせん「シガナイ」作曲家なのでは
あるが…。作曲すべき新作のために詩も新しく書かれる場合と、既存の詩をテキストにす
る場合とがある。前者の場合、詩ではなく、「詞」という字をあてたりするが、別に厳密
な区分けはないようだ。で、僕の場合、このふたつのケースの比率は七三で前者が多い。
もともと僕にとって、詩とは読むためのものであって、作曲するということとは、又違う
意識なのだ。学生時代から、たとえば青山の中村書店なる詩集専門の店へ通った。次々に
漁っては買い込み、読み耽った。僕の書棚には今も詩集がたくさん並んでいるが、それは
詩を「読む」楽しみのためだ。
さて今回、アルベルネユーゲントコールからの新作委嘱を受けるにあたっても、テキス
トをどうするか、が最初の問題であった。アルベルネの皆さんが、「合唱曲になりうるで
あろう」詩をいろいろ集めて下さり、僕がそれから選ぶことになった。安水稔和さんの2
冊の詩集に、僕の関心が集中した。「生きているということ」という詩集に惹かれた。
神戸在住の安水さんが、阪神淡路大震災で未曾有の体験をなされた、その中から生まれた
詩集である。惹かれたが、実は僕はすでに、「阪神大震災鎮魂組曲・1995年1月17日」と
いう合唱作品を書いていて、この曲は神戸の合唱団により、頻繁に演奏されている。
同じテーマを繰り返すのは、創り手としてはつらい。そこで選んだのが、本日初演の「鳥
について」を構成する5篇の詩であった。
鳥に関する詩から4篇、と「歌」。しかし歌と鳥は同義だ。従って全5篇が「鳥」であ
る。詩の使用をご快諾下さった安水さんに感謝している。5曲は、調性において循環する
関連を持っているので、これは「曲集」ではなく、明確に「組曲」である。7月末日に脱
稿。池田先生の指揮のもと、鳥のように飛翔するアルベルネの声がおおいに楽しみだ。
◇ ◇ ◇ ◇
池辺晋一郎氏のプロフィール
東京芸術大学卒業、同大学院修了。
在学中、音楽之友社室内楽作品懸賞第一位、第35回日本音楽コンクール作曲部門第一位
を受賞、その後今日まで活発な作曲活動を続ける。管弦楽、室内楽、声楽、オペラ、バ
レエのみならず、映画、演劇、テレビの音楽担当も多く、活躍の場は広く、各分野にお
ける受賞は、国内外で枚挙にいとまがない。かたわら、全国各地のコンサートホールの
企画委員やアドバイザーも務める。
日本作曲家協議会会長、東京音楽大学教授、日本音楽著作権協会評議員、日本音楽コン
クール運営委員
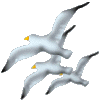
 ☆ゲストメッセージ−その2 へ☆
☆ゲストメッセージ−その2 へ☆

