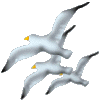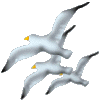
最初のコマーシャルソングとして認知されているのが、デンツァ作曲の「フニクリ・ フニクラ」です。120年前、ヴェスヴィァス登山電車のために書かれたこの歌は、ナ ポリを起点に世界の大ヒット曲となりました。浅学な私は、折り返しの部分“Jammo, jammo”が、何とAndiamo!(それ行け、行こう)の訛りとは気付かぬまま、永年歌い、 そして教えてもいました。音楽用語に酷使されているイタリー語には珍談が限りなくあ りますが、このコンサートはさしづめヤンモ、ヤンモなのです。 池辺さんとの付き合いは、私が新米の高校教師、彼がピカピカの一年生に始まりまし た。 テストの設問ppp(ppよりもっと静かに)に対し、ピアノトリオ(ピアノとヴァィオ リンとチェロの三重奏)の解答があり、私はその頓智を愛でて◎をつけました。いまだ に自供をしませんが、後輩の坂本龍一君は入学前なので、真犯人は明白です。 青臭い「楽譜に忠実!」を振りかざす私が、池辺さんの弾くピアノに文句を言い続け ていたら、合唱祭の本番で、ゲストだった作曲界の大御所、清水脩氏から「伴奏だけが オーケストラのよう」と激賞されて、私のメンツは丸潰れでした。 幾星霜を経て天才+秀才と大作曲家の誉れの極みに立った今も、「池田先生に頼まれ りゃ」とアルベルネからの委嘱に快く応じ、「まだ神様じゃないョ」との私のイジメに も耐え、超多忙の中、7月末に新合唱組曲「鳥について」を完成してくれました。 他の3ステージの練習で、この20数年前の作品たちが、色艶を少しも失っていないこ とに、驚き呆れる実感を味わっています。 安水稔和さんのお名前は、30余年前に芸術祭の受賞作品「京都」などで存じ上げてい ましたが、阪神淡路大震災の現地、神戸に踏み止まって詩集「生きているということ」 を著し、昨年の土井晩翠賞を受けられたと知って、そのヴァィタリティに感服したので す。 震災当時、神戸新聞論説委員長だった三木康弘氏の言葉をお借りします。「仕事に疲 れ切っているとき、あるいは、生きることの困難にぶつかって思わずその重圧に打ち負 かされそうになるとき、ぼくはつねに安水さんの詩を読むことによって、深い勇気と励 ましの力を与えられてきました。」 今回で18度めの協演となる西川さん、過密なスケデュールを繰り合わせて、オーヴェ ルニュを共有して下さる佐竹さん、三上さん、佐々木さん、伊藤さんにも感謝します。 これからのアルベルネが“Jammo, jammo!” となるのでしょうか。客席の皆様から のお見守りと、お励ましとをお願い致します。